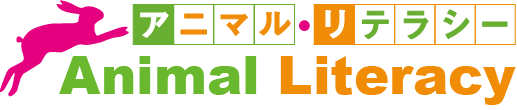無料記事38:恩恵をもたらす動物との関係、負の連鎖をもたらす関係
2025年11月10日 掲載
目次:
恩恵をもたらすものばかりに光が当たる、人と動物の関係
人間に恩恵をもたらす動物との関係
あまり光の当たらない、動物との負の関係
人と動物の関係の両側面を知る必要性
恩恵をもたらすものばかりに光が当たる、人と動物の関係
人と動物の関係というと、「動物の癒し効果」、「ペットを飼うと子どもの情操教育に良い」、「ペットの飼育は健康に良い」、「ペットと飼い主がお互いを思いやる絆」など、どうしても人間が恩恵を受ける関係やポジティブな関係をイメージする者が多いが、人と動物の関係は、互いに恩恵をもたらすプラスの関係ばかりではない。メディアなどで取り上げられる人と動物の関係も、どうしてもプラスの側面が多い印象が拭えず、マイナスの側面に光が当たる機会が少ないためか、人と動物の関係性にそういったネガティブな側面があることを認識していない者も多いように思える。本記事では、注目されることが少ない、人と動物の関係性のマイナスの部分に光を当て、人と動物の関係には正と負の両面があることをより多くの読者に知ってもらい、アニマル・リテラシーを身に付けてもらうことを目的とする。人間に恩恵をもたらす動物との関係
無論、動物との関係が人間に多くの恩恵をもたらす点については科学的な知見も蓄積されており、それを決して否定すべきではない。動物との関係に所謂「癒し効果」があるということは多くの者が認識しているところであるが、漠然とした癒しの効果以外にも、動物と関係を持つことによって受けることができる恩恵については様々な研究結果が報告されている。例えば、動物との関係は、認知的発達、さらには感情面や社会性の発達や、ソーシャルサポートなど、多岐にわたる側面から子どもに恩恵があることが報告されている。1)また、子どものペット飼育が精神上の健康に効果があることも報告されている。2)正に、「動物は子どもの情操教育に良い」ということである。
加えて、言わずと知れず、動物との関係は成人も含め幅広い健康効果をもたらすとされている。3)個人の身体的・精神的健康のみならず、動物が社会的潤滑油のような機能を果たし、地域社会の人間関係を活性化させることも示唆されている。4)ペットと共に暮らす多くの者たちが実感し、経験しているように、そしてたくさんの研究が指し示すように、動物との関係は我々人間に実に多くのプラスの効果をもたらしていることは否定のしようがない。
あまり光の当たらない、動物との負の関係
しかしながら、冒頭で述べた通り、動物との関係は諸刃の剣であり、そこには間違いなく負の側面も存在するということを決して無視してはならない。その代表的なものが、当法人が度々情報発信している動物虐待と対人暴力の連動性「LINK」である。人と動物の関係性が負の方向に歪んでしまった時、それが動物に対する暴力という形であらわれてしまうこともあり、その暴力の矛先が動物のみならず、人間にも向かってしまうリスクが高いと言われている。この動物虐待と人間に対する暴力の連動性は、海外では「LINK」と呼ばれているのである。実際、動物虐待が家庭内暴力や殺人などの凶悪犯罪を含む対人暴力、さらには多岐にわたる反社会的行動と連動している5)ことを示す研究は数多く世に出ており、人間と動物の負の関係性が個々人、さらには地域社会の安心・安全とつながっている可能性が高いということが言えるのである。さらには、積極的な暴力だけではなく動物のネグレクトという形で動物たちを苦しめるような動物虐待の種類もある。動物の世話を怠り動物たちに苦痛を強いるという負の関係もまた、人間側の当事者の健康問題、生活上の課題、公衆衛生上のリスクなど、人間側の生活の質全般と連動していることを示すケースも多々あることを忘れてはならない。さらに、動物たちに対する愛情や慈しみの心がある関係であるからこそ、それが諸刃の剣になり、私たち人間に負の影響を及ぼすケースもある。その典型的な例はペットロス、すなわち大切にしていた動物の喪失体験である。良好な関係を築いており、人間と動物の間に強い絆があっても、動物側の死をきっかけに、その関係性故に人間側に多大な精神的負担がかかる場合があることを、我々は改めて認識すべきであろう。実際、動物とのプラスの関係性(動物に対するプラスの態度)6)や愛着の強さ7)が、当該動物が亡くなった後の悲嘆と関連していることを示唆する研究もあり、動物との絆がポジティブで強固であるほどその動物が亡くなった後の人間の精神的負担が大きくなってしまうということも考えられるのである。
動物に対する慈しみの心が諸刃の剣となり、人と動物の関係から人間が負の影響を受けるケースであまり知られていないのが「共感疲労 (compassion fatigue)」である。ケアや支援が必要な動物に対応する支援者側には、動物との信頼関係を築くために、動物の立場に身を置き感じ、考えるという共感能力を発揮することが求められる。しかし、特に困難な課題を抱える動物たちの世話をする現場において、そのような課題を抱えた動物たちに寄り添うということは、動物たちの問題やそれにまつわる辛い状況・体験を自分事のように感じ、理解するということになる。さらには、課題解決に貢献できなかった場合、無力感などにさいなまれることもあろう。こういった支援が必要な者との継続的な接触や関係性の構築により支援を提供する側が被るストレスのことを「共感ストレス(compassion stress)」と言い、共感ストレスへの長期的な暴露による生物学的・心理的・社会的な疲労と機能不全状態のことを「共感疲労 (compassion fatigue)」というのである。8)
この共感疲労は、人間に支援やケアを提供する医療従事者のメンタルヘルスの課題としてよく知られているが、近年は動物のケアに従事する者の心の健康にまつわる課題としても注目されており、特に獣医療現場や動物保護団体・アニマルシェルターなどで働く者の共感疲労は欧米ではよく話題に上がる。実際、獣医療や動物保護など、動物を救うことを目標として選んだ現場で、動物の命を終わらせる安楽死の作業などにも従事せざるを得ない状況が特にメンタルヘルス上悪影響を及ぼす要素の一つとされ、関係者にとって大きなストレスとなるとされているこの状況・現象は「caring-killing paradox」として注目されている。9)また、ペット関連の動物のケア提供者のみならず、畜産動物や実験動物を扱う現場でも動物に辛い処置を施したり、動物の命を終わらせる処置に従事しなければならない場面もあることから、こういった現場の者たちも上述したような共感ストレスを被っていることが容易に想像できる。なお、共感疲労については、当法人のニュースレター(PDF)で特集号を販売しているので、ご関心のある方はそちらも参考にしてほしい。
動物との素晴らしい絆が人間にとって負担となってしまう場面はこれだけではない。例えば、緊急災害時などの場面においては、ペットが心の支えになるというストーリーはよく耳にするが、こういった状況でもペットとの関係は諸刃の剣となり得るのである。先に挙げたペットロスと関連し、災害などが発生すると不幸にもペットを失ってしまう者も出てくるが、こういったペットの喪失が災害後のストレスを予測する要素であることを報告する調査研究も出ている。10) また、災害時に大切な動物家族を置いて避難しなければならない状況に陥った場合、多くの飼い主が避難を拒んだり、一旦避難した後にペットを救出しに危険を冒して避難区域に戻ってしまい、人間側の安全も甚大な危機にさらされるということは、過去の災害の教訓として多くの関係者が認識している点であろう。人と動物の絆は素晴らしいものであるということは多くの者が実感している点であろうが、ひとたびそのいずれかの身に危機が迫るような緊急事態が発生すると、それをきっかけに、その関係が人間に負の影響を与えたり、人間側の安全を脅かす状況になりかねないということを我々は今一度肝に銘じておかなければならないのではなかろうか。
最後に、人間と動物の関係性の負の側面は心理的・精神的なつながりのみにとどまらないという点についても指摘したい。その良い例が、近年多くの関係者から懸念の声が上がっている、野生動物との過剰な接触である。野生動物を人間社会の懐深くに入れてしまうことにおける公衆衛生上のリスクについては以前の記事でも指摘しているところであるが、多くの新興感染症(新しい、今まで未知だった感染症)において人獣共通感染症が寄与していると言われており、その多くの発生源が野生動物であることが指摘されている11)ことなどから、動物によっては、適切な距離を保たないとその関係性が人間の身体的健康の側面からもリスクを伴うものになってしまうということも覚えておかなければならない。野生種を取り扱った展示施設や訪問活動などで「動物の癒しをお届けします」という謳い文句を頻繁に目にするが、実は野生動物との接触は癒しどころか、公衆衛生上の危険をはらんでいるという「リスク」の部分(※)をもっとたくさんの者たちにアニマル・リテラシーを身に付けた上で認識してほしいところである。
人と動物の関係の両側面を知る必要性
本記事で概観したように、人間と動物の関係には、皆が注目するような人間が恩恵を受けるプラスの側面がある一方で、一歩間違えれば私たち人間も動物も心身共に傷つきかねない負の側面もあるということを認識しなければならない。「人と動物の素晴らしい絆」に関するストーリーは耳触りがよく、どうしても皆そちらにばかり気が向いてしまうのは仕方のないことかもしれない。しかし、私たちが日頃から様々な形でお世話になり、関係性を築いている動物たちとの絆を冷静に、様々な角度から見ることができるようにアニマル・リテラシーを身に付け、その関係性が諸刃の剣となる場面もあり得ることをぜひ多くの読者に認識してほしい。負の側面について知って、知識を身に付ければこそ、そのマイナスな部分を回避したり軽減する意識や心構えを持つことができ、そこから具体的な対応策を講じることができるようになるのではないだろうか。(※) 実際、動物介在介入について専門的資料も多く世に出している有識者の国際的な集まりである「人と動物の関係に関する国際組織(IAHAIO)」は、野生種を所謂「アニマルセラピー」に用いるべきではないと勧告している。その理由としては、上述したような公衆衛生上のリスクや、動物の福祉を担保できないなど、両者にとって負の関係性となる恐れがある点が挙げられている。12)
- 1) Melson, G.F. (2003). Child development and human-companion animal bond. American Behavioral Scientist, 47, 31-39.
- 2) Purewal, R., Christley, R., Kordas, K., Joinson, C., Meints, K., Gee, N. & Westgarth, C. (2017). Companion animals and child/adolescent development: A systematic review of the evidence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14.
https://doi.org/10.3390/ijerph14030234 - 3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19185195/
- 4) Wood, L., Martin, K., Christian, H., Nathan, A., Lauritsen, C., Houghton, S., Kawachi, I. & McCune, S. (2015). The pet factor - companion animals as a conduit for getting to know people, friendship formation and social support. PLoS ONE 10(4), e0122085.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0122085 - 5) Vaughn, M.G., Fu, Q., DeLisi, M., Beaver, K.M., Perron, B.E., Terrell, K. & Howard, M.O. (2009). Correlates of cruelty to animals in the United States: Results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. Journal of Psychiatric Research, 43, 1213-1218.
- 6) Planchon, L.A. & Templer, D.I. (1996). The correlates of grief after death of pet. Anthrozoos, 9, 107-113.
- 7) Field, N.P., Orsini, L., Gavish, R. & Packman, W. (2009). Role of attachment in response to pet loss. Death Studies, 33, 334-355.
https://doi.org/10.1080/07481180802705783 - 8) Figley, C.R. (1998). Burnout as systemic traumatic stress: A model for helping traumatized family members. In Figley, C.R. (Ed.), Burnout in Families the Systemic Costs of Caring. (1st ed., pp. 15-28). Boca Raton, Florida: CRC Press.
- 9) Fournier, A.K. & Mustful, B. (2019). Compassion fatigue: Presenting issues and practical applications for animal caring professionals. In Kogan, L. & Blazina, C. (Eds.), Clinician’s Guide to Treating Companion Animal Issues Addressing Human-Animal Interaction. (1st ed., pp. 511-534). London: Academic Press.
- 10) Lowe, S.R., Rhodes, J.E., Zwiebach L. & Chan, C.S. (2009). The impact of pet loss on the perceived social support and psychological distress of hurricane survivors. Journal of Traumatic Stress, 22, 244-247.
- 11) Jones, K.E., Patel, N.G., Levy, M.A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J.L. & Dszak, P. (2008). Global trends in emerging infectious diseases. Nature, 451, 990-994.
- 12) https://iahaio.org/wp/wp-content/uploads/2021/01/iahaio-white-paper-2018-english.pdf