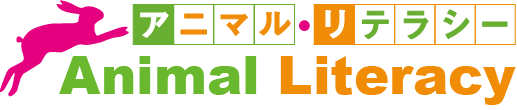|
【アニマル・リテラシー】動物関連トピックス 2020
|
投稿:2020年10月26日 16:30
家にネコがいます!
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 動物好きには面白いグッズを紹介した記事を共有します。 なんと、ネコを飼っていることをアピールするための自動車用マグネットステッカーがあるそうです(ただ、売上げは、動物保護団体に資金をチャネリングする法人に寄付されるそうです)。 寄付が有効活用されるということをのぞいては、一見ただの面白グッズですが、このように「自宅で動物を飼っている」という表示グッズは、災害時に大変役立つものなのです。 災害時、どうしても動物を置いて避難しなければならないこともあります。例えば、ネコなどの動物は地震のようなパニックになるようなことが発生した場合、真っ先に隠れてしまい見つからないということもあります。このような際、動物をその場からすぐに避難させないと命にかかわる場合(洪水が迫っている、火事が発生しているなど)以外においては、数日分の飲み水や食べ物を置いてとりあえず人間が避難するという判断も適切な場合があります。また、出先で災害が発生し、自宅に戻れなくなってしまった場合なども、動物のみが自宅に取り残されてしまうという事態になってしまうことが考えられます。 こういった場合、避難後に家屋の点検や人や動物の捜索に現場に戻った救助隊やボランティア等々の関係者に、「自宅に動物がいる」ということを知らせることは、大変意味のあることになります。このようなサインを玄関などの見える場所に貼っておけば、自宅の中に入って動物の様子をみてきてくれたり、救助してくれたりということにもつながります。 また、家屋の点検など、動物とは関係のない人間にとっても、建物の中に動物がいるということがわかれば、扉や窓を不用意に開けて、動物が逃げ出してしまうという事故を防ぐことにもつながります。実際、このような動物の存在を知らせる看板や張り紙のサンプルをペットの災害対策として配っている動物保護団体の事例もあります。 面白グッズ一つとっても、アニマル・リテラシーを身に付けていれば、様々な創意工夫を凝らしてグッズを活用することができるかもしれません... |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年10月20日 16:30
ゾウにやさしい紅茶
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 紅茶により、ゾウが被害にあっていることを知っていますか。 インドにおいて、紅茶農園の排水溝に落ちてゾウがけがをするケースが増えているそうです。茶畑がある地域は人が少ないため、妊娠したメスのゾウが安全な出産場所として使うことがあるそうで、生まれたばかりの赤ちゃんゾウが排水溝に落下して被害にあうそうです。 この課題に対応するために、「エレファント・フレンドリー」という紅茶農園の認証制度が設立され、ゾウが落下しないような配慮がされた茶畑で生産された紅茶に付加価値をつけるような取り組みが展開されているとのことです。 認証制度により、どの製品が動物に配慮して生産されているか、消費者もわかるようになります。 動物によりやさしい生活をしたい消費者は、このようなマークを頼りに商品を選択することもできます。私たちが動物と袖すり合っている意外な場面について知って、消費者として、自分の納得のいく選択をしたいものです。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年10月15日 17:00
かわいい動物ばかりに目が行きがちですが…
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 世界動物保護協会が始めた興味深いキャンペーンを紹介した記事を共有します。 「Ugly Animals Need Love Too(醜い動物も助けを必要としている)」というキャッチコピーを掲げ、かわいらしい動物と等しく、見た目がかわいらしくないと判断されるような動物たちや、私たちが普段関心を寄せることがないような動物たちも、助けを必要としている旨を伝える啓発動画を展開している取り組みです。 犬や猫など私たちに身近で、かつ一般的にもかわいらしいと見なされる動物の境遇は、メディアなどでも取り上げられやすく、人々の関心も集まりやすいと考えられます。一方、人間にとってあまり身近ではない動物、または外見が万人受けしないと判断されるような動物は、保護が必要でも日の目を見ることがないものもたくさんいます。真のアニマル・リテラシーとは、私たちにとって「かわいい」、「身近」な動物だけではなく、私たちが袖すり合うあらゆる生命に対して関心を寄せ、知識を高めることではないでしょうか。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年10月09日 17:00
犬は私たちの言葉を理解する!?
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 「良い子だね!」と犬を褒めた時、言葉を理解しているかのように、うれしそうにしている犬の姿は、誰にとっても微笑ましい場面だと思います。ところで、犬は本当に私たちが彼らを「褒めている」ことを知っているのでしょうか。 犬の脳が、私たち人間と同じように声がけを分析していることを示す研究結果が発表されたそうです。犬の脳は、人間のそれと同じように、話し言葉の音を階層的に処理しているそうです。原始的な脳の部位で音声言語の情動的な部分を分析してから、より新しい脳の部位で言葉の意味を分析するという仕組みで私たちの声がけを処理しているそうです。 私たちの声がけを処理する高度な能力を私たち以外の動物が有するということは、私たち人間が私たち以外の動物と様々なレベルで相互作用していることの裏付けになります。私たちと動物がどのようなレベルでかかわり合っているのか、このような基礎研究により得られた知見を活用し、アニマル・リテラシーを身に付けたいものです。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年09月17日 16:30
ジャガーの違法取引
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 近危急種として個体数の減少が懸念されているジャガーの違法取引が近年増加していることをご存じですか。 中南米において、違法取引が多発しており、調査などによると、建設現場などで働くために入国する中国人労働者がこのような違法取引にかかわっている場合が多いとのことです。 中南米においては、麻薬や武器の取り締まりに注力してきており、このような動物の違法取引については見過ごされてきた可能性もあり、動物やその身体の部位の違法取引の実態のさらなる調査や今後の対策が待たれるようです。 なお、この記事によると、ジャガーの身体の部位が違法取引される背景には、トラの代用として使われているという点があるそうです。 関係者がアニマル・リテラシーを身に付け、違法取引が発生する背景の調査や、末端の消費者の啓発などを含めた包括的な対策が進むことを期待したいです。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年09月08日 16:30
イエネコの祖先の歴史
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー イエネコの起源に迫る、中欧におけるヤマネコの暮らしと人間との関係性を紐解いた記事を紹介します。 ネコは私たち人間にとって、とても身近な動物の一つであり、また家畜化されたネコたちは、私たち人間社会の一員でもあります。 そんなネコたちと私たちの社会の関係性の起源を知ることで、より豊かに共存できるヒントを得ることができるかもしれません。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年09月03日 16:30
動物園の意義
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー イギリスにおける、動物園の意義に関する議論をまとめた記事を紹介します。 これまでは、多くの動物園が「エンターテインメント性」を重視した展示を展開させてきたという流れがありますが、動物への配慮を求める消費者の意識が高まるにつれて、動物園の意義が問われ始めています。 動物園の中には、野生動物の保護・保全や教育を掲げて運営されている施設もありますが、果たして動物園はどれだけこれらの課題に貢献しているのでしょうか。 日本においても、同じように動物園の意義が問われ始めています。関係者一同がオープンにこのような議論ができ、動物園の将来のあり方が社会的意義を持ったものとなることを期待したいです。 また、消費者もアニマル・リテラシーを身に付け、日頃訪れる展示施設について考える必要があるのではないでしょうか。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年08月25日 16:30
高齢者とペット、その支援は…
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 近年だいぶメディアも取り上げられるようになった、高齢者とペットの様々な課題について、読みやすい簡単な記事を紹介します。 加齢と共にペットの世話が十分にできなくなってしまったらどうしようか... 万が一自分が入院・入所しなければならない場合、ペットの面倒を頼める人がいないから医療福祉サービスを使うのをためらってしまう... このように、高齢者の生活の質や、場合によっては社会福祉の支援のスムーズな利用にかかわるペット問題は、人間を対象とした社会福祉と動物問題が交差する領域に対応する「Veterinary Social Work (VSW)」の分野でも大きく取り上げられる課題です。 この記事では、高齢者のペットの飼育支援などを展開しているVESENAという獣医師の団体も紹介されています。 ヒューマンサービスと動物関係の様々な関係者が連携して、高齢の飼い主とペットを上手に支援できる社会が実現することを願うばかりです。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年08月17日 17:00
そり犬の遺伝子の歴史
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 私たち人間は、様々な犬種を作り出し、中には作業犬として、その労働力で私たちの生活を支えてくれている犬種もいます。そんな労働で私たちを支えてきたそり犬として使われる犬種が、9500年前に既に確立さており、大昔からそりを引いて私たち人間を手助けしていたことをご存じですか。そり犬の遺伝子を分析した興味深い研究結果に関する詳細を記した記事を紹介します。 また、記事中にあるように、そり犬の遺伝子を受け継ぐ現在の犬種をペットにした場合、彼らと幸せに暮らすヒントも記載されています。 このような基礎研究により動物に対する理解が深まり、得られた知見が私たちと動物がより豊かに共存できるヒントとして活用されることを期待します。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年08月04日 16:30
イルカは道具を使う!?
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー イルカが道具を使って狩りをすることをご存じですか。しかも、道具を使う狩りの方法を、親ではなく、同世代の仲間から学ぶことをご存じですか。 同世代の仲間で技術の伝達が発生するのは、これまで人間と類人猿でしか確認されておらず、イルカでは初めて確認されたとのことです。 オーストラリアのシャーク湾のイルカを観察し様々なデータを集め、狩りの伝達パターンのコンピューターモデルを作るという研究で判明した知見です。このような知見の蓄積により、私たちは袖すり合って生きている動物たちのことについてより理解を深めることができます。また、彼らへの理解を深めることが、より良く共存できる世の中の礎となることを期待したいです。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年07月28日 16:30
犬にも「思春期」が存在する!?
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 犬にも人間と類似した「思春期」が存在することを示す研究が発表されたそうです。 盲導犬の候補犬と飼い主(パピーウォーカー)を追跡調査し、親子関係を調べるという調査が実施されたそうです。結果、人間の思春期の親子関係同様、思春期にある子犬は、飼い主への従順さを低下させていることを示唆する「紛争的行動」を起こしやすいことが示され、飼い主に対する愛着が不安定になっているメスの子犬は、早期の性成熟を果たすことが示唆されたそうです。 長年人間のパートナーとして共に生活してきた犬ですが、彼らとの関係をさらに豊かにするヒントとなるような知見をもたらす研究ではないでしょうか。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年07月16日 16:30
地震に影響される、マッコウクジラの生活
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 大きな地震の影響により、マッコウクジラがその後1年間、餌を取る行動を変化させていたことを報告する研究が公表されたそうです。 地震とその後の津波により、クジラたちが餌としている生物たちが一気に遠くに流されてしまい、餌が乏しい環境となってしまったため、クジラたちは餌を探すためにより深く長く潜り、またそのために餌をとる間に海面で休憩し、体力を回復させる時間も増えたことが観察されたそうです。 地震が陸生動物に及ぼす影響を調査した研究は存在するものの、海中に住む生物がどのような影響を受けるか調査した研究は、とても貴重だそうです。 自然災害は、私たち人間の生活に大きな被害を及ぼしますが、野生動物たちも当然影響を受けるのです。当法人のFBページでも度々扱っている、人間と動物(そしてさらには環境)の状態や福祉が連動しているということを指し示す「ワンウェルフェア(one welfare)」の概念の具体例のような、環境(災害)、人間、動物の連動性を示唆する研究として捉えることもできます。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年07月06日 17:30
フラミンゴの社会でも「親友作り」が重要!?
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 私たち人間のように、フラミンゴも「親友」を作るということが研究により明らかになったそうです。 フラミンゴの社会形成を調査するために、5年に及ぶ追跡調査を実施したところ、フラミンゴも人間のように、特定の個体と安定した関係を築くことが明らかになったそうです。また、特定の相手を避けるということも明らかになったそうです。 記事中にあるように、フラミンゴの社会のあり方を理解することにより、保護活動の改善につながる知見として活用できる可能性もあります。 このような動物たちの文化や社会を理解する基礎研究は、私たちとその動物のより豊かな共存に役立つ知識となりうるかもしれません。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年06月23日 16:30
馬は、知っている人間を写真で見分けることができる!?
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 馬の、人間の認識力に関する興味深い研究結果をまとめた記事を紹介します。馬が、信頼関係がある人間と見知らぬ人間の写真を見分けられるということが研究により示されたそうです。 コンピューター制御された画面上に映し出される写真を選択することを馬に訓練で教えた後、見知らぬ人と飼育員の写真を見せたところ、75%の確率で、見知らぬ人の写真を無視し、飼育員を選択するという結果が出たそうです。 過去に馬の世話をしていた飼育員を識別することもできたそうです。 馬が見慣れた人間とそうでない者の顔を区別することができ、かつ臭いなどの手がかりがなく2次元表現でもそれができることが示されたとのことです。また、馬が長期記憶を持つ可能性も示唆されたそうです。 馬は、太古の昔から私たち人間と共に生活する家畜です。そんな長い間関係を築いてきた馬たちのさらなる理解につながり、より上手に共存するための礎となる知見ではないでしょうか。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年06月17日 17:00
ネコたちを大追跡!
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 「キャット・トラッカー」というプロジェクトをご存じですか。6カ国で900匹以上のネコにGPS装置を1週間装着し、ネコたちの行動場所と範囲を調べるというプロジェクトだそうです。 このプロジェクトの結果が論文として発表されたのですが、下記の記事はその調査結果をまとめたものです。このプロジェクトによると、多くのネコは、自宅の近くで大半を過ごし、行動範囲も狭いということが示されたそうです。 しかしながら、その狭い行動範囲で集中的に狩りを行ったりするので、その地域の生態系に及ぼす悪影響が懸念されるということが指摘されています。 また、この調査では、ネコたちが6日間の追跡中に平均4.5回道路を渡っていたことも明らかになりました。このようなことから、外飼いのネコについては、交通事故が現実味を帯びた危険因子であるということも示されたということになります。 この研究結果を見る限りにおいては、ネコは室内飼いのほうが、ネコの福祉や安全にとっても、周囲の環境にとっても良いのかもしれません。このような調査が、私たちとネコがより深い絆を結び、より良く共生するために活用できる知見となることを期待します。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年06月08日 16:30
動物同士の「共通言語」!?
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 犬と馬の、遊ぶ際に展開させる行動がよく似ていることが、研究でわかったそうです。全く異なる動物種である犬と馬が、「共通の言語」を持っているということです。 噛む振りをする、物を使って遊ぶ、素早く相手の表情を真似る「高速表情模倣」という行動までも、共通するそうです。 この研究で得られた知見は、「遊び」という行動が種の垣根を越えて、普遍的に存在するということをも示唆するものだそうです。 私たちが袖すり合う動物たちのコミュニケーション方法や、その営みについて理解を深めるために、このような研究で得られた知見が役立つことを期待しています。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年06月04日 16:30
外来種としてのミシシッピーアカミミガメ
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 日本でも急激に数が増えており、在来種や環境に影響を及ぼしているミシシッピーアカミミガメですが、ニューヨークでもこのカメが同じように、在来種の減少や環境の変化に寄与しているそうです。 ニューヨーク市の条例では、ペットを放すことは禁止されているそうですが、実効性を担保するのは難しいというのが現実のようです。 中学校の理科の教師が、この社会問題について、子どもたちを教育している様子も記事にて描かれています。ご関心のある方は、ぜひご一読ください。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年05月26日 16:30
高齢ペットの介護の現状
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 高齢のペットの飼い主を対象とした調査によると、高齢犬・猫に対する配慮で実施していることがあると回答した飼い主は約7割、また約8割の飼い主が介護が必要なペットを飼っていると回答したそうです。 イオンペットが、自らが運営するペットの火葬・葬儀ができる霊園検索のためのウェブサイト「メモリアルなび」にて調査した結果です。 獣医療や飼養管理方法が進歩するにつれて、ペットもより長生きするようになった昨今、高齢のペットの介護や世話により飼い主に負担がかかるというケースは増えているようです。 ペットサービスの業界にとっては、増加する飼い主のニーズを分析するために、一般の飼い主や、ペットを飼うことを検討している方にとっては、動物を家族として迎える際に「覚悟」しなければならないことや、必要なリソース(時間、お金、労力、サービス)などをじっくりと考えるために役立つ知識なのではないでしょうか。ぜひ記事をご覧になってアニマル・リテラシーを身に付けてください。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年05月19日 16:30
動物も数を認識する!?
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー ハチ、鳥、オオカミなどの多くの動物種が、数を理解して、それをもとに行動していることが明らかになったそうです。 餌を探す・もらう時の数の違いの認知や、さらには相手と争うか逃げるかなどの判断においても、動物が数を数えていることを示すヒントがあるそうです。 私たちが普段から袖すり合っている動物の知性や認知力などを知ることも、アニマル・リテラシーを身に付ける上で重要ですし、彼らとよりよく共存する一助となるかもしれません。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年05月14日 16:30
ゾウたちを守る武装レンジャー
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー アフリカのチャドの国立公園におけるレンジャーの活動に関する記事を紹介します。 この国立公園は、アフリカン・パークスというNPOの武装されたレンジャーが密猟者たちからゾウを守っている地域です。 レンジャーたちが国立公園を管理するようになってからはゾウの犠牲が減ったそうですが、同時にレンジャーが密猟者に襲われ殺害されるという事件も少なからず起こっているようです。 違法行為をしている密猟者は決して許されませんが、その多くが生活に困窮しているなど、社会的な要因が潜んでいることも多々あります。 また、ゾウを守ることも大切ですが、そのゾウを守るために身体を張っているレンジャーたちの安全も決して無視できません。 そして、何より人間の都合で個体数が減ってしまったゾウたちの境遇を改善することが急務です。様々な要因や視点が交錯する課題であり、アニマル・リテラシーを身に付けて考えていきたい問題のひとつです。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年04月21日 16:30
野良犬も人間の出すシグナルを読み取れる!?
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 私たちのパートナーとして長年人間と共に暮らしてきた犬ですが、研究により、人に飼われたことのない野良犬でも、人間のジェスチャーを理解できるということがわかったそうです。 野良犬は世界中にいますが、狂犬病などの人獣共通感染症の感染源となったり、人間に危害を加えることもあったり、人間の生活を脅かす存在ともなりえます。 このため、一部では野良犬の個体群を非人道的な方法で処分してしまうなどの事態が発生しています。 今回の研究では、人間の指さしを野良犬がどのように読み取るかということが調査されたそうです。 結果、犬は人間の合図に込められた意図を判断し、それをもとに意志決定するということが示されたそうです。 また、それをもとに得られた情報を処理する能力も備わっていることも示されたとのことです。 結論として、人間のジェスチャーを理解して活用する能力においては、野良犬も他の犬と遜色ないということがわかったということです。 人間のジェスチャーをわかるということは、野良犬と地域の人間の共存の糸口になり得るかもしれません。 また、私たちが長年パートナーとして共に生きてきた犬たちの能力に対して認識を改めるきっかけにもなる研究です。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年04月15日 17:00
昆虫は「痛み」を感じるのか?
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 昆虫の「痛み」に関する記事を紹介します。 近年、昆虫を含めた無脊椎動物が痛みを感じるか否かに関する研究が盛んに行われているそうです。 「動物は感覚のある生命体」という理解は多くの先進国の動物福祉法・動物保護法に反映されています(日本の動物愛護法にはこのような文言は現時点では含まれておりません)。また、世界各国をみてみると、一部の頭足動物を「保護動物」に含む動物関係の法規制も存在します。 無脊椎動物に、私たち人間と同様の「意識」が存在するのかという点については、科学者により意見がわかれるそうですが、今やこのような無脊椎動物の「痛み」が論点になる時代なのです。 私たちが日常的に袖すり合っている様々な動物についてより理解を深める知見です。また、私たちがお世話になっている動物たちに対してより適切な配慮をするために役立つ知識の礎となりうる研究の分野です。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年04月06日 17:00
動物保護に厳しいスイス
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー スイスは最も厳しい動物保護に関する規制を有している国と言われていますが、その内容をまとめた記事を紹介します。 スイスの動物福祉の政策や法令については、中には「ここまでやらなくても...」と思う方もいらっしゃるかもしれません。 最終的な落としどころはさておき、動物福祉は、世界中の国や様々な機関が絶えず議論している課題の一つです。世界中の人々が、どのように動物が扱われるかについて関心を高めており、世の中では動物に対する配慮がより重要な立ち位置を占めるようになってきたことは間違いありません。 その理由の一つはもちろん動物に対する私たち人間の倫理観ですが、それ以外にも、近年は「One Welfare」や「One Health」など、動物の福祉や健康が人間のそれと相関関係にあり、動物にやさしくすることが、人間社会にとってもメリットのあることという考え方が台頭してきているからとも考えられます。一般社会も、動物福祉やそれに付随する「One Welfare」などについて真剣に考えるために、アニマル・リテラシーを身につけなければならない時代がきているのかもしれません。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年03月24日 16:30
動物も、仲間を助ける!?
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー ヨウムが自ら進んで仲間を助ける行動を展開することを示す研究結果を紹介した記事です。 二つの部分に仕切られた透明なガラスのケージのそれぞれの部分に、人間にコインを渡すとナッツがもらえることを学習したヨウムを入れ、その2羽のどちらかだけにコインを渡すと、コインをもらえなかった仲間にもコインを分け与えるという行動を展開させたそうです(詳しい研究方法などはぜひ記事をご覧ください)。 群れで生活する動物は、利他的であると、「いいやつ」の評判が広がり、結果良い仲間に恵まれるという効果があるため、このような行動を展開させるように進化したのではないかと考察されています。 チンパンジー、吸血コウモリや、ドブネズミなどもこのような仲間を助ける行動を展開するそうです。 動物は、時には私たちが想像する以上に複雑な行動や思考を持って自分たちの社会を形成していることを改めて感じるような研究結果です。私たち人間は、アニマル・リテラシーを身につけ、彼らについて、そして私たちと彼らの関係のあり方について、きちんと考える必要があるのではないでしょうか。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年03月11日 16:30
ペットの災害対策
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 東日本大震災が発生して9年目の節目となる日なので、ペットの災害対策に関する記事を紹介します。 以前より当法人としても指摘してきたように、ペットの災害対策は、動物を助けるという観点からのみではなく、動物を家族と捉えている「人間」の健康や安全、さらには公衆衛生上の観点などからも対策が必要な課題です。 しかしながら、記事中に示唆されているように、避難所など不特定多数の方々が利用する施設においては、アレルギー対策や、動物の飼養管理、動物が入れる場所・入れない場所など、適切な取り決めを事前に整備しておくことが必要不可欠です。何よりも、動物の飼い主が、平時よりできる限り備えておくことが大前提になります。 動物だけではなく、飼い主である人間の支援としてという広い視野と、日頃から備えておくように促すための飼い主教育、避難所などの体制について事前の取り決めを整備しなければならない自治体など、多面的に対策を講じなければなりません。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年03月04日 17:00
「ライオン牧場」
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 南アフリカには、「ライオン牧場」という施設がたくさんあることをご存じですか。 触れ合いや写真撮影などの娯楽のためにライオンを繁殖している施設で、中には国際的な非難の的となっている「キャンドハンティング」(canned hunting, 動物たちを、逃げ場がない囲いの中に「缶詰」状態で放して行うスポーツハンティング)のためにライオンを供給しているところもあります。 ライオン牧場の中には、動物たちを劣悪な施設に保管しているところもあり、動物保護団体の調査によりしばしば悲惨な状況が明るみに出ているようです。 この問題も他の動物問題同様、様々な社会的課題と密接に関係しています。例えば、「動物虐待」と世界的に非難を浴びている「キャンドハンティング」は、南アフリカの観光産業を支え、国の経済にとって不可欠であると主張する者たちもいます。 ライオンたちの境遇を改善することはもちろん、アニマル・リテラシーを身に付けた広い視野を持って解決する必要がある課題であると感じます。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年02月28日 14:30
アメリカで飼育されているトラたちの実態
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー アメリカにおいて飼育されているトラの現状に関する記事を紹介します。絶滅の危機に瀕しているトラですが、アメリカ国内では現在、世界に生息する野生の個体数を上回るトラが飼育されているそうです。 飼育は、トラと触れ合ったり、写真を撮ったりするための娯楽目的の商業施設が主だそうですが、このような施設のためにトラを繁殖する「トラ牧場」においては、トラが劣悪な飼育環境の中で繁殖させられているそうです。また、成体になり触れ合うことが危険となったトラが処分されていることも多々あり、その身体の部位を国外において売買する密輸ネットワークもあるとのことです。 最近、SNSなどでも見映えの良い写真が撮れることから、野生動物との写真撮影や触れ合いは消費者にとって人気のアトラクションとなっているようですが、その背景で、動物たちがどのような扱いを受けているのか、消費者として、アニマル・リテラシーを身に付けたいものです。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年02月18日 16:30
犬とブタのコミュニケーションの違い
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 最近一部でペットとしてのミニブタが流行っていますが、犬とブタの人間との交流の特徴を調べた興味深い研究に関する記事を紹介します。ペットのミニブタのかわいらしい動画付きの記事です! 人間とかかわる時のそれぞれの特徴がよくわかる記事です。犬はブタよりもはるか昔に家畜化され、また人間と共に作業をするために交配されてきた動物種であるため、人間のあらゆる情報を読み取ることが極めて重要な要素であったことが説明されています。 一方で、ブタは主に食肉のために家畜化された動物であるため、人間の指示をあまり見ていないとのことです。また、ブタは身体的構造上、首をあまり長い時間上げていることができないため、視覚的な指示を読み取るのは不得手のようで、コミュニケーションは嗅覚に頼ることが多いそうです。 人間との相互作用の仕方が動物種によって異なることを示す興味深い研究です。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年02月04日 16:30
畜産動物の福祉のあれこれ
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー オルタナ編集部が少数の大手食品会社に対して実施した、動物福祉に関する各社の方針についての調査の記事を紹介します。 各社に対して、動物福祉に関する方針を設けているか、鶏のバタリーケージやブタのストール飼い(それぞれ鶏やブタを身動きできない狭いケージに入れて管理する方法)に対して取り組みを実施しているかなどを調べたアンケート調査です。 また、この記事には、BBFAW(Business Benchmark on Farm Animal Welfare, 畜産動物福祉に関する企業のベンチマーク)のグローバル企業の評価対象となった日本の食品企業が、いずれも最低ランクの評価であった旨など、動物福祉に関する取り組みにおける日本の企業の立ち位置についても書かれています。 動物が好きな消費者にとって、動物に配慮して製品が作られているかという点は、その製品を選ぶ基準の一つになり得ます。また、一消費者として、知った上で人道的な選択ができるように、このような点においてアニマル・リテラシーを身に付けることは、責任ある消費者としての第一歩であると考えます。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年01月28日 16:30
昆虫の違法取引
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー 野生動物の違法商取引や密輸については、当法人のFBページでも度々扱っていますが、昆虫の闇取引についての記事を紹介します。 昆虫は小さく、あらゆる所に生息しているため、このような密輸について問題視する人があまりいないようですが、記事中にあるように、乱獲により昆虫そのものが絶滅の危機にさらされるのはもちろん、その土地にいない生き物を持ち込むことは、偶然付着していた新たな寄生虫を持ち込んだり、逃げ出した昆虫がその土地の生態系を荒らしたりと、環境に重大な影響を及ぼす危険性もあります。 無脊椎動物と言えど、アニマル・リテラシーを身に付け、私たちとどのように袖すり合っているのか、きちんと知っておきたいものです。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年01月20日 17:00
AI技術が野生動物保護に貢献!?
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー グーグルが、野生動物用画像認識ツールを開発したというニュースを紹介します。 野生動物保護のためには、生息している個体数の調査がかかせない作業ですが、このような調査は、動物が生息する地域に動く物に反応して撮影するカメラを設置し、写った動物の個体をカウントする形で実施するそうです。今回開発されたツールは、この画像に写った個体の数をAIにより自動解析できるようにするツールだそうです。 このツールにより、個体数調査がより効率よく実施でき、結果、保護活動がより迅速に進むことが期待されているとのことです。 動物の保護は、多くの「動物好き」が関心を寄せるテーマですが、動物を保護する過程は、実際の動物を救護して世話するだけではありません。このような裏方の作業や保護に伴う情報処理などで、実際に動物に触れる飼養管理や獣医療の技術以外にも、様々な分野の技術が役に立っているのです。こう言った観点からも、動物に直接関わる技術者のみならず、幅広い職業がアニマル・リテラシーを身に付ける必要がある時代になってきているのではないでしょうか。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |
投稿:2020年01月10日 17:00
猫と人間の絆
| 内容 | 【動物関連ニュース】ー しばしば「独立心があり自由気まま」というイメージを持たれがちな猫ですが、犬と同じように飼い主との絆があることを示唆する研究が公表されたそうです。 この研究では、セキュア・ベース・テスト(secure base test) という保護者との絆の形成を評価する方法を用いて、猫が飼い主を「安全な基地」として認識しているかどうかということが検討されたそうです。 その結果、今回の研究に参加した猫の2/3が、不慣れな環境において飼い主を安全な基地として認識し、絆を形成しているということが示されたそうです。この割合は、人間の子どもや犬においてこのテストを実施した際の割合と一貫した結果だそうです。 人間のパートナーというと「犬」というイメージを持つ方も多いことと思いますが、私たち人間は、実に様々な動物とかかわりを持ち、絆を持っていることを改めて実感させられる研究結果です。 |
| 参考サイト | 参照サイトへ(外部リンク) |