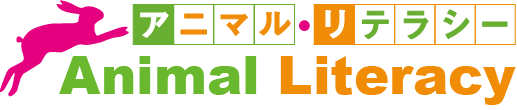無料記事1:動物から見た世界の動き
2017年11月28日 掲載
動物から見た世界の動き
日本という島国では、情報網が発達した今日においても動物関連の世界の動きがなかなか一般市民の耳に届かないようである。動物から見た今の世界の先進的動きとは、一体どのようなものであろう?一度彼らの立場に身を置いてみると、色々なものが見えてくるようである。
農業動物の世界
人間の食を支える動物たちの扱いは、先進国では年々向上している。戦後の高度成長期の需要を賄うために畜産はどんどんと「工場化」していった。その中で、動物が命あるものであるということが忘れ去られてしまったことは言うまでもない。
1964年と言えば、日本人にとってはあの記念すべき東京リンピックの年であるが、動物の世界では英国にて初めて工場的畜産の是非が問われ、その内情を探る公的委員会、ブランベル委員会が発足し、現在動物福祉の世界的基準となっている5つの自由が提唱された年である。
それから長い年月が経ち、今では国外の各地にて鶏のバタリーケージ飼いが禁止されたり、生体の輸送時間や距離に規制がかかったりと、農業動物の扱いに大改革の時代が訪れているようである。しかし、これは決して動物が可愛そうという観点からの改革ではない。むろんそのような側面もあることは事実であるが、畜産の現場の改革は、人間の健康に大きな影響を与えるのである。現在米国議会で大きな論争となっているのは、畜産業界での抗生物質の使用である。過密な工場生産体制におかれる家畜は、ストレスから病気になりやすい。そのために、抗生物質がしばしば病気予防や成長促進を目的として用いられている。米国では、医療の現場で使用されている量をはるかに超えるものが畜産業界で活用されているようである。
そのため、我が国でも問題視されている耐性を持つ病原体が出没してしまうのである。これは人間の健康を脅かす恐ろしい事態であり、早急に対処しなくてはならないことである。むろん入手方法に規制をかける法律が手段とされてはいるのであるが、ストレスがあまりかからない健全な飼養管理体制を整えることも重要な要素である。家畜にとっての良質な飼育体制は彼らを「幸せ」にするのみならず、人間の体を守ることにもつながる。
またこの飼育体制に関しては最近学会で興味深い講演があった。2016年のIAHAIO(人と動物の関係に関する国際会議, International Association of Human Animal Interaction Organizations)パリ大会の基調講演において、カナダのフレーザー博士(Dr. David Fraser)は、飼育環境を例えば鶏の放し飼いのように整えても、物理的条件が同じ養鶏場を比べてみると、個体の負傷率や死亡率などが大幅に異なる実態があると発表した1)。
その訳を調べてみると、原因は飼育員にあったそうである。沢山の飼育員を置いているところよりも、限られた人数の飼育員が常に鳥たちに関わっている農場のほうが各個体の状態が良いということが判明した。それは決まった飼育員たちが常に鶏の様子を観察しているので、良い意味で「つながり」ができ、鳥たちにかかるストレスも少ないということである。また、このつながりは飼育員の観察眼にも大きな影響を与えているのであろう。これぞ正に「人と動物の関係学」的要素である。
その他にも畜産の現場に関しては多くの課題があるが、今や世界、特に欧米社会においては、このような課題に関する人々の関心が高まりつつある。我が国でも大量集客を実践しているコストコは、米国店舗にて平飼い・放し飼いの鶏卵を大量に仕入れるようになった。
それは顧客が求めたからである。「ここには平飼いの卵はないのか?」と聞かれれば、ビジネスとしてはその声を無視することはできぬ、とコストコは言っている。日本では、その声をあげる者が極めて少ない。それ故に改革は必要ない、と生産者は思ってしまうのである。やはり島国なのであろうか…
自然と人間、そして動物
人間ほど、他種の特性を劇的に変えてしまった生き物はいない。原始人は、自然の力に対抗し何とか生き延びるよう努力をしていたが、今や自然が人間に対抗し何とか生き延びる努力をすることを迫られているのである。他の動物種をこれほど多くこれほど短時間で絶滅に追いやった生き物は他にはいない。
1980年頃には、古代から続いた熱帯雨林の4分の1以上が破壊されていた。この熱帯雨林は、今地球上の総面積のわずか3パーセントであり、かつ地球上の生物(人間がすでに発見しているもの)の半分以上がそこを住みかとしているのである。人と動物の関係の中で、今最も重要視しなければならない課題の一つであろう。人が生きていくためには、様々な生活活動を展開させる。しかし、その中には自然とその中に住む動物たちを追い詰めてしまう活動もある。
それを直ちに改めることは困難であるが、まずは問題点を一般大衆が認識することが大切である。この点に関しても、我が国の国民意識が未発達であると感じざるを得ない。例えば象牙問題であるが、日本は中国と並び一大消費国である。ゾウの密猟が原産国でいかに横行しているか、ゾウの数がどのような速度で減少し続けているか、これは世界のメディアや動物関連団体がしばしば取り上げる問題であるが、残念なことに日本国内では今一つ盛り上がらない話題である。半世紀前はアフリカ大陸で1千万頭、2千万頭、とも言われていたゾウの個体数が最近ではすでに50万頭を切っている。WWFは、2013年には推定400トンの象牙が不法取引の対象になったと発表しているが、これはゾウ約5万頭に匹敵する量である。
国によっては、2009年から2014年までのわずか5年間でゾウの生息数が4割も減ったところもある。このような世界状況の中で、米国の前政権、オバマ政権時代には中国の習近平首相との間で話し合いが持たれ、中国は世界最大の消費国として禁止に等しいような商取引の厳しい規制を象牙に課したのである。最近日本においても環境保護団体などの抗議活動が展開されてきた結果として、楽天が象牙商品の取り扱いを停止したが、我が国では全体的な市場として合法的な取引しか行われていない、と言い切れるのであろうか?密猟と象牙の売買は貧困層が多い国々においては極めて魅力的な仕事であろう。またテロ組織の資金源にもなっていると言われている。
沢山の兵士やレンジャーを配置しても、広大な土地の中で密猟を防ぐことは不可能である。このような課題に取り組むためには、関係者がみな自らの責任を果たさなければならない。当然消費国も責任を負うべきであろう。しかし、消費者である国民が問題の重篤度を理解していなければ、何も変化は訪れない。このような絶滅危惧種の問題は、我々アジアにも大きな影を落としている。アジアの希少動物であるオラウータンは現在インドネシアのボルネオやスマトラに約6万頭が生息していると言われているが、毎年相当数の個体が命を落としている。
その最大の理由が、ヤシ油農園による森林伐採である。「エコ」という言葉に促され環境にやさしいヤシ油の世界的需要が高まっているその中で、住みかを奪われる動物たちが出てくるのである。2014年にマレーシアとインドネシアでヤシ栽培に開拓された650万ヘクタールのうち約400万が熱帯雨林であった。10年後にはオラウータンはいなくなると言う者もいる。住みかを奪われるだけではなく、ヤシの新芽が好物であるオラウータンは、農園にとっては害獣であり駆除されてしまうこともしばしばある。保護団体などが農園で捕獲された個体を数十万円で買い取ることもやっているが、新芽を食べに農園に忍び込む個体を止めることはできない。
ヤシ油の現状に取り組むために、現地及び欧州などの有名ブランドのメーカ―が集まり、より良心的な生産体制を支えることに合意し原生林の開拓やオラウータンの生息地の侵害などを行わない生産者のみを使うことになったが、今後の展開はまだまだ予断を許さないものである。
人間が環境に一方では配慮しながら、その反対側では動物たちを悲惨な目に合わせてしまうという究極のパラドックスであろう。
展示動物の世界
日本動物園水族館協会と世界動物園水族館協会との間に追い込み漁で捕獲されたイルカの売買に関する大きな問題が生じたことは、まだ我々の記憶に鮮明に残っている最近の出来事である。最終的には、世界動物園水族館協会のメンバーとして日本が残留することに落ち着いたが、ここにも我が国の閉鎖的体質が浮き彫りにされている。米国カリフォルニア州サンディエゴ市にある世界的に有名なシーワールドで、シャチのショーが行われなくなったことも近年の話である。
その原因に、一つは訪問者たちをはじめとする一般大衆がSNSなどを通してシャチの不自然な姿は見たくなと主張したからである。英国やスイスなどヨーロッパでは、イルカなどの展示を禁止している国もある。全世界では現在推定2000頭前後のイルカ・シャチなどが展示されているそうであるがその約4分の一が日本国内で飼育されているのである。展示施設は、「人気のイルカショーを楽しみにしている国民がいるからである」と主張しているが、我々国民は本当にそれを望んでいるのであろうか?それとも何も知らされていない無邪気な子どもとしてそれを見せられているのであろうか?世界から白眼視されている日本の展示動物の現状は他にもある。すでに亡くなってしまっているが、生前井の頭で飼育されていたゾウのはな子である。
何十年もの間、孤独な独房生活を強いられてきたと海外ではSNSが炎上した。群れで生活する習性のある動物を一頭飼いすることは、精神的に極めて酷なことである。また、世界動物保護協会(現World Animal Protection, WAP, 旧World Society for the Protection of Animals, WSPA)、の動物展示施設評価票には、全面コンクリートの展示は評価するまでもなく「失格」であると記述されている。はな子の展示に非難の声が世界的に上がったのは、そのようなこともあるのであろう。それに対して、園側はしっかりとした反論をしていない。
また、国内メディアもしきりに「はな子を愛している」という武蔵野市民のインタビューを登場させていた。これはどのように捉えるべきであろう?そして、はな子の死後記念碑を立てるために大きなお金が動いた。生前のはな子の住居の改善に、どうしてこのようなお金が使われなかったのであろう?不思議極まりない。今や欧米では、動物園やサーカスなどの改革運動がどんどんと進み始めている。つい最近、米国最大手であり世界のサーカスの最高峰とも言われてきた老舗のリングリングブラザースが廃業宣言をした。人が動物との関係を再考察する時代がやってきた、一つの証であろう。また熱帯の動物を寒い地域で飼育することの問題に対処するため、何年か前にデトロイト動物園は、ゾウの展示を閉鎖しゾウ達を米国内南部にあるサンクチュアリーに送った。どれだけ獣医療や動物舎にお金をかけても、冬場の皮膚の問題などが解決できないということに基づいた大きな決断である。
このような動きが各地で起こっていることが、どれだけ日本国内で知れ渡っているか… 明治の評論家である斎藤緑雨の名言の中に、無知は憎むべきものであるが、無邪気は可愛げのあるもの、しかし無邪気は無知の一つであるという趣旨のものがあるが、正に人間と動物の関係においては、これは多くの我が国の国民に当てはめられるべき言葉なのかもしれぬ。
アニマル・リテラシーを高める
一昔前は、このようなことを唱えれば「犬猫大好き人間の愛護活動」と社会から揶揄されていたかもしれぬが、今や多くの国際的場面においても人間が自分と時空を共にする動物たちのことをもっと知らなければならぬという気運が高まっている。動物が可愛そうである、愛護、保護しなければならぬ、という考え方はむしろ人間のおごりである。動物たちは、我々人間に守ってもらおうなどとは考えてもいない。彼らは、彼らなりに人間という厄介な存在との折り合いをどうつけようかと悩んでいるかもしれない。
我々とて同じである。娯楽の中で、作業の補助として、食糧として、科学の発展のために、あらゆるところで人間と「袖すりあう仲」である動物たちの現状を知るところから、我々人間は自らの落としどころを模索していかなければならないのである。肉を食べること自体が悪いことでもなく、動物を人工飼育することが非難されるべきことでもない。
しかし、それをするにあたっては、人間は最低限の責務として実態を知る努力をするべきであろう。これも人類の進化の一つと捉え、無知も無邪気も乗り越えていかなければ、人は人ではなくなってしまう。
1) Fraser, D. (2016, July). Animal welfare ethics, science and the human dimension. Plenary lecture conducted at the 14th International Conference of the International Association of Human Animal Interaction Organizations, Paris, France.