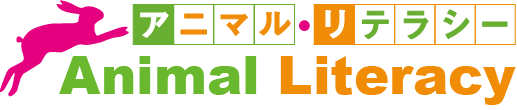無料記事37:「動物問題」というと、何を思い浮かべる?〜動物について視野を広げることの意義〜
2025年9月17日 掲載
目次:
日本で「動物問題」というと…
海外で話題に上がる「動物問題」
犬猫問題についても視野を広く持つ者も
視野を広げ、様々な動物にかかわる課題について知ることの意義
日本で「動物問題」というと…
「動物問題」と聞いて、どういったことを思い浮かべるだろうか。この記事を閲覧している多くの読者が、「殺処分ゼロ」や「悪徳ブリーダー」など、「犬猫」を中心としたペットの問題を想起するのではないだろうか。「動物問題」イコール「犬猫問題」という一般的な認識は海外でも同じかというと、犬猫にかかわる課題はやはり多くの者が認識している主要な問題である一方、特に欧米では動物の専門家ではない一般の消費者でも動物に関心があったり、動物好きであれば、「動物問題」というと犬猫にとどまらず、それ以外の様々な課題を思い浮かべる者が日本の一般消費者より圧倒的に多いという印象がある。メディアにおいても、「殺処分ゼロ」や「悪徳ブリーダー」などの犬猫に特化した問題だけではなく、犬猫以外の様々な動物たちが抱える課題が取り上げ、それらを一般の読者が目にする機会も多い。
それでは、海外で「動物問題」というと、一般の消費者は「犬猫」を中心とした課題以外にどのようなものを思い浮かべるのであろうか。本記事では、海外で一般的に話題に上がる「動物問題」について概観し、「犬猫問題」以外にも視野を広げて世界的な動向を把握することが、いかに意義があることであるかという点について考察したい。
海外で話題に上がる「動物問題」
それでは、海外の一般消費者は、犬猫以外の話題でどのようなことを気にしているのだろうか。
多くの一般の「動物好き」な消費者は、動物に関する消費者意識を高めることにつながるような社会的課題について問題意識を持っている。私たち人間は、ペットを飼っていなくても、実に様々な動物に日常生活を支えてもらっている。例えば、私たちの食卓に上がる食べ物の多くは、農業動物がもたらしてくれる。また、医薬品や化粧品などを含む様々な製品を開発したり、使用する人間にとって安全であることを確認する安全性評価の作業においては、多くの実験動物が使われている。動物好きであれば、自分が使う製品や自分の生活において、どのような動物が使われており、その動物たちがどのような扱いを受けているのかという点について気になるということは、言われてみれば自然な流れである。実際に、動物の専門家ではなくただ単に動物好き、ペットを飼っているというだけでも、特に海外の市場においてはこういった点を気にした消費活動を展開させている消費者や、必ずしも消費活動に反映させていなくてもこういった知識をアニマル・リテラシーとして身に付けている消費者は多い。実際、欧州連合(EU)において化粧品の動物実験が禁止された際には、動物に対する配慮を求めた消費者が起こした市民運動が大きな機運を作ったと言われており、数年前には動物保護団体や化粧品企業が協力して世界的に化粧品の動物実験を禁止するよう求める署名を800万件以上集め、国連に提出している1)などということを鑑みても、一般消費者のこういった課題に関する関心が高いと言えよう。
日本においては、一般の動物好きの消費者で、このような課題について認識している者はまだまだ限定的であるように思え、またこういった課題を当たり前のように取り扱う海外メディアと比較して、日本のメディアにおいて犬や猫などのペット以外の動物に関する社会問題が取り上げられる機会も限られているような印象が拭えない。例えば、日本特有のこういった「動物の消費」に関する課題で、動物の関係者間では世界的に話題となっている問題の一つが象牙の市場である。ゾウが密猟により絶滅の危機に瀕していることは誰もがどこかで聞いたことがある話題であろうが、その密猟の背景には、象牙などのゾウ由来の製品に需要があり、これらが高値で取引されるということがある。そして、日本をはじめとしたアジア各国は象牙の一大市場なのである。もともと象牙の取引は厳しく規制されていたものの、ゾウの個体数が急激に減少しているなどの背景もあり、2016年のワシントン条約第17回締約国会議で、各国に象牙の違法取引に寄与することがないよう、あらゆる施策を講じるように求める決議10.10の改正2)が採択された。そこから、中国を含む象牙の市場を抱える各国が禁止を次々と表明しているが、取引の規制を表明する国内民間企業が出てきたり3)、象牙の年代証明に関する規制が強化されたりするものの4)、徹底した対策について遅れをとっている日本が、ゾウの保護に取り組む関係者の非難の的となるようになってしまうのである。5), 6)
しかし、話題となっており、しかも他国よりも規制が緩い象牙の市場を未だに抱えているということから非難される日本の一般消費者は、果たしてどの程度この問題について知っているのだろうか。動物が好きであったり、動物に関心を寄せる者であっても、ゾウが絶滅の危機にあることは聞いたことがあっても、そのような話題と象牙の印鑑や民芸品など、身の回りに何気なく置かれている雑貨に結び付きがあることを認識している者はそう多くはないのではないだろうか。動物由来の製品やサービスを使う、使わないは個人の自由であり、各々が納得のいく選択をすれば良いが、動物にお世話になる一消費者として、無知であることはその「動物問題」と紐づくその他の社会的課題にも無関心ということになり、その無知・無関心が結果として人間社会をもむしばむことになりかねない。
犬猫問題についても視野を広く持つ者も
世界各国では、もちろん犬や猫などのペットにかかわる課題もよく取り上げられる旨は前述した通りであるが、特に関心の高い者たちや専門家などを見てみると、日本の同等の層よりも、動物に関する課題をより広い視野で捉えているという印象がある。例えば、世界的な動向として、動物にかかわる様々な関係者や専門家において、人間と動物双方の福祉や健康が密接につながっているという認識はますます顕著になっていっているのではないだろうか。そして、こういった意識を持つ者が増加の一途をたどっているというだけではなく、実際にこの視点をそれぞれの仕事や活動の場に活かすというさらに一歩踏み込んだ実践への応用も多くみられるようになってきている。こういったものの例として、当法人が度々情報発信している動物虐待と対人暴力の連動性「LINK」における様々な実践上の取り組みが挙げられる。子ども虐待、ドメスティック・バイオレンス(DV)や、高齢者虐待などの家庭内暴力がペットの虐待と連動して発生しているリスクが高いという知見を活かし、家庭内暴力に対応する社会福祉当局と、動物虐待に対応する動物保護当局が相互通報や情報共有体制を敷いたり、お互いが管轄する暴力についてお互いをトレーニングし合うような取り組みは、特に北米において多く見られる。また、海外の当局では、「アニマル・ホーディング」と呼ばれる多頭飼育崩壊のケースにおいても、動物保護関係者だけではなく、社会福祉、公衆衛生、消防、警察などの複数の分野の当局がチームになって課題に対応しているケースもある(アニマル・ホーディングに関しては、環境省のガイドライン7)にも事例が掲載されている通り、日本においても少しずつではあるが、社会福祉当局などと動物愛護当局が何らかの形で連携している自治体も出てきている)。
上記のように、一見すると「犬猫問題」で片づけられてしまうような課題についても、人間のメンタルヘルスや生活上の課題と密接につながっているという専門家の認識は、特に欧米諸国では深まってきているようであり、これに対して日本の動物やヒューマンサービスの専門家の中で、人間と動物が密接な関係性にあるという認識や、そういった知識を実際の実践に役立てようとする視点を持っている者はまだまだ少数派なのではないだろうか。
視野を広げ、様々な動物にかかわる課題について知ることの意義
上記で概観したように、世界的な動向を見てみると、人々の話題に上がる動物問題は決して犬猫などのペットに関するものだけではない。専門家のような動物関係者はもちろん、一般の動物好きの消費者も、多岐にわたる動物たちに関する様々な社会的課題に目を向けているのである。
実際、一般社会が「動物の問題」と捉えている課題の多くは、動物だけにとどまらず、様々な社会的課題と密接に関係している。例えば、上述した動物虐待と対人暴力の連動性やアニマル・ホーディングなどの課題が物語っているように、動物にかかわる課題は人間の健康や福祉にかかわる課題と連動して発生していることが多い。このため、動物にかかわる課題は決して「かわいそうな動物を救わなくては」という道徳的な使命だけに突き動かされて取り組むべきものではなく、そこにいる人間も動物も支援の手が必要な危機的な事態となっている可能性を鑑みた対応が必要なのである。
私たちが「消費」している農業動物や実験動物などにかかわる課題でも、人間の生活に直結するものが多々ある。例えば、農業動物の福祉やその生産体制は、食の安全や公衆衛生と密接に関係しており、動物実験に関する課題は製品の安全性(ひいては人間の健康)や、科学技術の進歩と切り離せない。「動物問題」と聞いて犬や猫にかかわる課題を真っ先に思い浮かべるのではなく、様々な動物たちにまつわる多岐にわたる課題が見えるように視野を広げておくことは、人間の生活の安心・安全、公衆衛生、環境問題等々、幅広い社会的課題に目を向けるきっかけとなる。そして、人と動物双方の幸せと生活の質の向上に向けた糸口となることであろう。
1) https://www.cosmeticsdesign-europe.com/Article/2018/10/05/Animal-testing-global-ban-UN-receives-major-petition
2) https://www.env.go.jp/nature/kisho/kisei/cites/resolution/conf_10.10_rev.cop18.pdf
3) https://www.afpbb.com/articles/-/3241924
4) https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42762800S9A320C1CR0000/
5) https://www.asahi.com/sdgs/article/14599023
6) https://toyokeizai.net/articles/-/154156
7) https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0303a/full.pdf