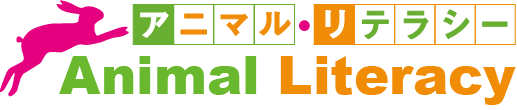無料記事21:
動物福祉とは?動物の幸せや生活の質を科学的に評価する指標
2022年9月20日 掲載
2025年5月12日 更新
目次:
動物福祉とは?5つの自由とその歴史
飢えと渇きからの自由
不快からの自由
痛み、傷害、病気からの自由
恐怖や抑圧からの自由
正常な行動を表現する自由
動物福祉の5つの領域
動物福祉とは?5つの自由とその歴史
動物と共に暮らしている、または動物に携わる活動や仕事をしている際、動物の保護者や飼養管理責任者として配慮しなければならないのが、「動物の生活の質は担保できているか?」、もっと砕けた言い方をすれば「動物は幸せか?」という点であろう。この点を客観的かつ科学的に評価できる考え方として、「動物福祉」という概念が台頭し、最近では日本でも徐々に定着しつつある。動物福祉とは、動物の心身の健全さ、そして動物の様々なニーズが満たされているかについて、科学的に検討するための概念である。国際的に使われよく知られている指標には、「5つの自由 (The Five Freedoms)」というものがある。これは、動物のニーズを5つのポイントに分類してわかりやすくまとめたものである。
5つの自由が提唱されたきっかけは、1960年代に、畜産動物を狭い場所に閉じ込め大量生産し、効率化と生産性を求めた「工場」のような生産体制について、市民より動物たちへの配慮を求める声が上がり、イギリス政府が畜産動物の福祉について調査・検討するための委員会を発足したことにある。1965年に、委員長のロジャー・ブランベルを筆頭に、委員会が提出した畜産動物の福祉に関する報告書、通称「Brambell Report」1)において記載されていた動物のニーズにかかわる文章「An animal should at least have sufficient freedom of movement to be able without difficulty, to turn round, groom itself, get up, lie down and stretch its limbs」が起源であり、これが後に畜産動物福祉審議会(Farm Animal Welfare Council, 現在は畜産動物福祉委員会(Farm Animal Welfare Committee)に代わっている)により拡大され、動物の主要なニーズ五つを列挙した現在の形の「5つの自由」に発展したのである。
現在では、この5つの自由の概念は、イギリスやニュージーランドなど、外国の動物関連の法令にも飼養管理者が担保すべき動物のニーズとして落とし込まれていたり、国際機関などに動物福祉の指標として採用されたりしている。まさに国際的な動物福祉の指標としてスタンダードとなっている概念であり、理想的には、その誕生のきっかけとなった畜産動物や私たちの身近なペットなどはもちろん、実験動物、展示動物、そして使役動物など、私たち人間が飼養管理下に置いているすべての動物の福祉の評価に用いられるべき動物の基本的なニーズについて考える枠組みなのである。
5つの自由は次の5項目により構成されている。
飢えと渇きからの自由
動物に適切かつ栄養上十分な食事と、適切かつ新鮮な水が与えられているか。例えば、夏の暑い季節に犬を外飼いしており、苔むしたボウルに汚れた水がわずかしか入っていない状況に遭遇した場合、この「飢えと渇きからの自由」が満たされていない状況であると言えよう。不快からの自由
動物が不快にならない環境が提供されているか。気温、湿度や床材等々、動物にとって適切な環境が整備されているか、また動物が雨風などの悪天候から身を守るための隠れ場所があるか、そして動物が置かれている環境において動物にとって物理的危険を及ぼす物が置かれていないかなどが含まれる。例えば、実験動物の管理施設や触れ合い動物園などの展示施設の中には、ワイヤーメッシュの床の動物舎の中で動物が飼養管理されている場合があるが、ワイヤーメッシュの床は動物にとってあまり居心地の良い場所ではなく、動物が過ごせる場所がこのような床材のみの場合、特にげっ歯類などは足の裏を損傷してしまうことがあり、「不快からの自由」が担保されない状況になってしまう(ワイヤーメッシュの床材にかかわる動物福祉上の提言として、米国学術研究会議発行の「Guide for the Care and Use of Laboratory Animals」(pg. 51-52)2)を一例として挙げる)。痛み、傷害、病気からの自由
病気や怪我の予防や健康管理が適切にされているか、さらには万が一病気や怪我が疑われる場合、適切な獣医療を提供しているか。例えば、いわゆる多頭飼育崩壊と呼ばれるアニマル・ホーディングの現場では、複数の動物がネグレクトされ、怪我を負ったり病気にかかっていたりする動物も適切な獣医療を受けることができず放置されている場合が多々ある。これは、「痛み、傷害、病気からの自由」を満たしていない状況である。恐怖や抑圧からの自由
動物にストレスや心理的不安がかかっていないか。例えば、家庭内暴力とペットの虐待は同じ家庭で連動しているリスクが高いとされているが、動物が直接暴力の連鎖に巻き込まれなくても、絶え間なく暴力が発生している環境に身を置くことが動物の精神的な負担となっていることを指摘する研究者もいる。ドメスティック・バイオレンス(DV)と動物虐待の連動性の研究3)の中には、DV被害者の実体験として、犬を連れて家庭内暴力から逃げ出しあと、犬がストレス性の皮膚疾患を発症し、安楽死を考えるまでにひどい症状が続いたなど、暴力が蔓延する家庭においてペットが不安やストレスなどの精神的な負担を被っていることを示唆する点が報告されている。このような状況においては、「恐怖や抑圧からの自由」が担保されていないことが推測できる。正常な行動を表現する自由
動物が本来自然に展開させる行動を表現できるような適切な環境や空間が与えられているか。これには、本来単独行動する動物、群れで行動する動物など、動物本来の社会的環境も含まれる。例えば、鶏は皮膚や羽についた寄生虫などを落とすために砂浴びする習性があるが、前述した「工場畜産」においては、採卵鶏はバタリーケージという狭いケージの中で飼養管理されており、砂を与えられておらず、この本来展開するはずの行動を表現できない環境下に置かれている。このような状況は、「正常な行動を表現する自由」が満たされていない状況の一例と言えよう。なお、5つの自由については、公益社団法人日本動物福祉協会が、わかりやすく箇条書きにまとめたウェブページ4)を公開しているので、ぜひそちらも参考にしてほしい。
動物福祉の5つの領域
近年、この5つの自由がさらに進化し、動物福祉の5つの領域(The Five Domains of Animal Welfare)として整理されている。デイビッド・メラ―により提唱された5)この5つの領域モデルでは、動物の福祉は身体的・機能的状態を構成する四つの領域(栄養、環境、身体的健康、行動6))と精神的体験の領域(すなわち精神状態)で構成されているとされている。栄養、環境、身体的健康、行動の身体的・機能的状態を構成する四つの領域において、動物はそれぞれプラスまたはマイナスの精神的体験をする。例えば、「栄養」の領域においては、適切な食事の欠如は、飢餓感の体験へとつながるが、適切な食事の提供により、動物は満足感や食事の味や香りがもたらす快感を体験するという具合である。身体的・機能的状態を構成する領域それぞれにおいて動物が経験した精神的体験が、五つ目の領域である動物の精神状態にフィードバックするのである。そして、栄養、環境、身体的健康、行動及び精神状態の五つのすべての領域のプラスとマイナスの精神的体験を総合し、動物の福祉の状態が評価されるというわけである。
この動物福祉の5つの領域モデルの利点は、動物の福祉を損なうマイナスな状況の回避に主眼を置いた5つの自由と異なり、飼養管理者がより良い福祉の状態を作り上げるために積極的に行動できるような視点が取り入れられている点であると言われている。動物福祉の5つの領域モデルにおいては、すべての領域において、動物がプラスの精神的体験を経験しているか、マイナスの精神的体験を経験しているかで総合的に動物の福祉を評価する。したがって、各領域において動物によりプラスの体験や感情を経験してもらい、動物の福祉にさらに「加点」しようというマインドセットを飼養管理者側において醸成することができる枠組みなのである。
5つの自由は、シンプルで誰にでも簡単に理解できる指標であるという点が強みである。この指標を当てはめて動物のおおよその状況を推し量ることも決して複雑な作業ではない。一方、上述した5つの領域のモデルは、考え方が少々複雑ではあるものの、「マイナスの側面を取り除く」という視点だけではなく、「あらゆる側面で動物により良い体験をしてもらうために、ポジティブな側面を増やそう」と飼養管理者がより積極的に動物の福祉の向上に取り組め、さらには動物福祉にかかわる諸要素をより細かく評価できる視点を提供するものである。動物園・水族館などの動物の展示施設、実験動物施設、畜産の現場や動物保護施設など、複数の動物を専門的に管理しなければならない現場における動物のプロにとっては、より視野の広がる視点かもしれぬ。動物福祉の概念がより洗練され、理解が深まる中、これらの考え方がどのように進化していくのか、そしてそれにより、動物に対する私たちの理解や付き合い方がどのように変化するのか、今後の展望を注視していきたいところである。
1) Report of the Technical Committee to Inquire into the Welfare of Animals Kept under Intensive Livestock Husbandry Systems: https://edepot.wur.nl/134379
2) https://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals.pdf
3) Taylor, N. & Fraser, H. (2019). Companion Animals and Domestic Violence Rescuing Me, Rescuing You. Cham, Switzerland: Palgrave MacMillan.
4) https://www.jaws.or.jp/welfare01/
5) https://www.mdpi.com/2076-2615/7/8/60
6) 最新の5つの領域モデルの論文では「行動」の領域は「環境・他の動物・人間と交流する際の行動(Behavioral Interactions)」と改められている:https://www.mdpi.com/2076-2615/10/10/1870/
2025年05月12日追記
当法人では、動物福祉について、様々なリソースを提供している。中には無料のものもあるので、動物福祉についてさらに知識を身に付けたいという読者はぜひ活用してほしい。
無料記事
・無料記事25: 愛玩動物看護師と動物福祉・無料記事26: 袖すり合う動物たちの福祉について考える
無料動画
・動物福祉って?5つの自由について知る_①飢えと渇きからの自由・動物福祉って?5つの自由について知る_②不快からの自由
・動物福祉って?5つの自由について知る_③痛み・負傷・病気からの自由
・動物福祉って?5つの自由について知る_④恐怖や抑圧からの自由
・動物福祉って?5つの自由について知る_⑤正常な行動を表現する自由
・動物福祉の観点から、愛玩動物看護師の役割を考える